| round18『Don’t Stop The Fire』 |
「聞こえなかったか? そこに落ちているパンケーキを食べろ、って言ったんだよ」 だらだらと汗を流して立ちすくんでいるシゲルに、俺は再度命令を下した。 王様にでもなった気分だった。 重罪の証拠をつかんだ今、俺はシゲルの運命を意のままに操ることができる。 しかし、余興はここまでだ。 「なんてな。冗談だよ。あんたと違って、俺に男を屈服させて喜ぶ趣味はない」 表情こそ変わらなかったが、シゲルはこの一言でいくらか警戒を解いたようだった。 中腰になってテーブルの横で固まっていたカスミも、小さく胸を撫で下ろしていた。 さて、そろそろ本題に入るとしよう。 仇敵の弱みを握った俺が、やつに望むことはただひとつ。 「もう一度俺と勝負をしろ、シゲル。人生を賭けた、男同士の勝負をな」 「……勝負だと?」 「そう。こいつは言わば、おまえが逃げ出さないようにするための保険だ」 ICレコーダーをコインのように宙に放り投げ、しっかりとこの手に握りしめる。 こいつを然るべき場所に持って行けば、シゲルを窮地に追い込むのは簡単だ。 だが、復讐を完成させるにはそれだけでは足りない。 今やつが立っている高みからやつを見下ろして、はじめて俺の復讐は完成するのだ。 そのためには、俺が俺自身の力で成り上がる必要がある。 「俺は必ずここから這い上がる。あんたを超える、ビッグな男になってやるよ」 みずからの手で、失ったものを取り戻す。 シゲルに引導を渡すのはそのあとだ。 「ふん、なにを言い出すかと思えば、お得意の戯言か。これまでろくに社会復帰もできなか った貴様に、今さらなにができる」 「なんだってできるさ。なんせ俺は、夏見英一の息子だからな」 親父の名前を出してやると、苦虫を噛みつぶしたようだったシゲルの顔に変化が訪れた。 やつの社長室で復讐を宣告したときと同じ、狩猟者の顔。野心家特有の笑み。 そう来なくては面白くない。 なぜならこれは、復讐という名のゲーム。 この世でもっとも甘く美しい感情を知る者同士の、一世一代の大勝負なのだから。 「勝負と言ったな。詳しいルールをお聞かせ願おうか」 「なに、ルールなんて簡単さ。俺は地位と名誉を手に入れる、あんたはそれを迎え撃つ。そ れだけだ。ただし、俺がこいつを持っていることを忘れるなよ。途中退場は認めない。それ と、カスミみたいにまた誰かを利用しようもんなら、俺はいつでもあんたの首を斬って落と すぜ」 「カスミに裏切られたことをまだ根に持っていたとはね。どこまでも執念深い男だ」 「人生を狂わせるのは、俺とあんただけでいい」 シゲルの肩越しに、カスミと目が合った。 この野良犬の姿をしかとその目に焼きつけろ、カスミ。 戦うっていうことがどういうことか、俺がおまえに見せてやる。 幸せは誰かに与えられるものじゃない。 勝ち取るものなんだ。 「あんたを地獄に突き落とすのは、この勝負に勝ってからのお楽しみに取っておいてやる」 「いいだろう。その勝負、受けて立とう」 「あとで吠えヅラかくなよ」 挑みかかる俺と、王座を守る立場となったシゲル。 竜虎相見える。 「全身全霊で這い上がってやる」 「全身全霊で叩き落してやる」 再戦の火蓋が、切って落とされた。 シゲルのマンションを出ると、俺とハルカは並んで大きく息を吐いた。 肩の力が抜けて、昨夜から張り詰めっぱなしだった神経が一気にほぐれてゆく。千秋楽を 終えた舞台俳優のような気分だった。 「本当によかったの? 渡貫社長に喧嘩ふっかけたりなんかして」 「おまえのほうこそどうなんだよ。愛人だったんだろ?」 「なっ……!」 ハルカの顔が、酸性を示すリトマス試験紙みたいに赤く染まった。 「誤解しないで! 私と渡貫社長は断じてやましい関係ではありません!」 「じょ、冗談だよ。そうカッカすんなって」 「どうして男の人ってそういう発想しかできないのかしら。本当嫌んなる!」 思わぬところに地雷が隠されていた。わかったわかったと言ってハルカをなだめながら、 俺は今後この女の前では下ネタは封印しようと心に誓った。あまりからかい過ぎると、いつ かの政治家みたいに気絶させられそうだ。 「で、これからどうするの? 大見得切って出てきたけど、働くアテはあるの?」 朝陽を受けて光る豊洲の海を見つめ、胸を張って答えた。 「ま、なんとかなるだろ。なんせ俺は――」 「夏見英一の息子、でしょ?」 「そういうことだ」 俺たちは顔を見合わせて笑った。 この先、俺たちの行く手には数えきれないほどの艱難辛苦が待ち受けているだろう。 それでも大事なものがあれば、へこたれるほどキツいことなんてなにもない。 「私も仕事探さなきゃね」 ハルカはぴしゃりと自分の頬を張り、俺に握手を求めてきた。 「お互い頑張りましょう。もう会うこともないでしょうけど」 「かもな」 「電話してきてくれたら、愚痴くらいなら聞いてあげる」 「おまえがまたクビになったら、いつでも俺の胸を貸してやるよ」 ばっかじゃない、と言って俺の肩を叩くハルカ。 これから俺たちは、別々の道を行く。 だが、きっとまたどこかで出会う。それも遠くない未来に。 手を振って別れたあと、なんとなくそんな予感がした。 「仕事を辞めた!?」 気分転換を口実に連れ出した井の頭公園で、ヒカリはボートがひっくり返りそうなほどの 大声で驚きを示した。彼女がこうもはっきりと感情を表に出したのは、いったいいつ以来だ ろう。 俺は湖を渡るほかのボートと接触しないよう気を配り、ゆっくりとオールで水を切る。 ヒカリと井の頭公園を訪れるのは、これで二回目だ。 「そろそろ潮時かと思ってさ。借りた金のぶんはちゃんと働いたし」 「で、でも……仕事辞めちゃったら、どうやって生きていくの?」 「また働けばいい。生きていくためなら、マグロ漁でもなんでもやるさ」 精いっぱい明るく言ってみせても、ヒカリは浮かない顔だった。 「心配するなよ。ヒカリのぶんも俺が働く。贅沢はできなくなるだろうけど、一生懸命働け ば、生活費くらいはまかなえるだろ」 親父と墓参りをしたときから、そうしようと決めていた。 昨年の六月、ヒカリは絶望の底に沈んでいた俺を拾い、面倒を見てくれた。 俺にはその恩を返す義務がある。 そこにどれほどの苦労が伴おうとも、ヒカリを見捨てたりはしない。 「だからもう、絶対に死にたいなんて言わないでくれ」 「……いいけど」 殴りつけるような風が雑木林をわななかせ、ヒカリは寒そうに身を縮こまらせた。 俺たちを乗せたボートは、逆風の中を進んでゆく。 「なぁ、ヒカリ。むかしよくいっしょにオンラインゲームで遊んだよな」 「遊んだけど、それがどうかしたの?」 「協力してレベルを上げたりして、楽しかった」 「いっぱい時間あったもんね」 「今だって、時間はいくらでもあるさ」 八十歳まで生きるとして、あと五十六年。 それだけあれば、人生を隅から隅まで遊び尽くせる。 「俺はまた一からレベルを上げていくよ。オンラインじゃなくて、オフラインの世界でさ。 最初は勝てない敵や行けない場所もあるかもしれない。だけど投げ出さずにちょっとずつ経 験値を積んでいけば、たいていのことはクリアできる。そうだろ?」 「そっか、そうだね……」 ヒカリの顔が優しくほころぶのを見て、俺は思わずうるっときてしまった。 この身にどんな不幸が降りかかろうと、生きてさえいれば、こうして再び大切な人の笑顔 を見ることができる。 ――生きていて、よかった。 「まずは職業を決めないとね」 「だな」 大事なものが、俺に戦う勇気を与えてくれる。 俺たちを乗せたボートは、もうすぐ岸に辿り着く。 その夜、ひさしぶりに氷の彫像に取り囲まれる夢を見た。 ただし今回は悪夢ではない。 長く俺を苦しめ続けてきた裏切り者たちとも、ついにお別れだ。 「ちょっとアンタ、なにやってんのよ!」 「なにって、見りゃわかるだろ。ここから脱出するんだよ」 夢の中で、俺は子供のころに憧れたショベルカーを操り、鍾乳洞の壁を削り取っていた。 いざショベルを振り下ろしてみると、凍てついた岩壁は驚くほどもろかった。 俺は氷漬けの世界に穴を開け、新しい世界への一歩を踏み出すのだ。 「やめろ! ここを出たって、どうせまた現実に押し潰されるに決まっている!」 「そのとおりだ! おまえは働く才能のない、生きる価値のない人間なんだからな!」 氷の彫像たちは口々に俺を罵ったが、耳を貸すつもりはなかった。 才能がなければ、人一倍努力すればいい。 生きる価値がないというのなら、俺が自分で作ってやるさ。 ――それができると信じる心さえあれば、世界に風穴を開けるのは簡単だ。 「ほら、出口が見えてきたぜ」 削れた岩肌の隙間から小さな光が射し込み、暗闇に覆われていた鍾乳洞を照らす。 俺はショベルカーを操る手を休めず、岩壁に開いた穴をさらに広げていった。 操縦席から手を振り、光に焼かれて溶けつつある氷の彫像たちに別れを告げる。 「今まで世話になったな。俺がくじけそうになったら、また夢の中に現れて叱ってくれ」 そして俺は、岩壁に最後の一撃をくわえる。 大きな音とともに出口が開き、やがて氷の世界はまっしろな光に包まれて消えていった。 明くる朝、空港でアメリカに戻る親父と浪子を見送った。 「お金に困ったら電話してきな。酒代くらいなら都合したげる」 「おまえの手なんか借りなくたって、自力で稼ぐさ」 「骨のある男になんなさいよ。お父上みたいにっ」 親父の腕にしがみつき、うねうねと腰をくねらせる浪子。 俺といっしょに二人を見送りにきた大木戸さんは、片道の恋に破れて魂が抜けたような顔 をしていた。昨晩からずっとこんな調子らしい。浪子も罪作りな女だ。 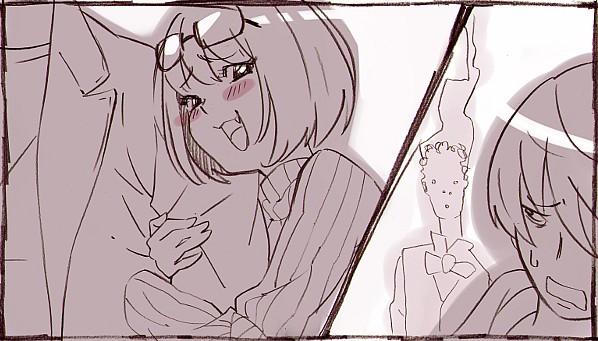 別れ際、親父は俺の背中を抱いてこう言った。 「しっかりやれよ、マイサン」 任せろ、と答えて拳と拳を突き合わせる。男と男の約束だ。 再会を誓い、親父と浪子は夢の国アメリカへと旅立った。 次に会うのはいつになるかわからない。だが、それまでに必ずまともな職に就き、二人を あっと言わせてみせる。 婚活が振り出しに戻った大木戸さんを慰め、俺は外に出ると青空に向かってうんと伸びを した。 「さて、ハローワークにでも行くとするか!」 俺もここから、新たなる旅に出発だ。 こうして、俺はおよそ一年ぶりに就職活動に復帰した。 毎朝アバハウスのスーツに身を通し、ハローワークで求人を検索する日々。 しばらく人生をさぼっている間に、求職者を取り巻く状況は激変していた。鳩だか宇宙人 だか、とにかく人外の生命体が政権を掌握して以来、日本の不況は悪化の一途を辿ってい る。中小零細の企業はそろって門戸を閉ざし、職歴も資格もない人間においでおいでと手を 振るのは、パチンコ屋か王将フードサービスかというご時世だ。 だが、粘り強く探せば、きっと仕事の口はある。 肝心なのは、諦めない執念だ。 ハローワークに通い詰めるかたわら、俺はアルバイトに精を出した。ヒカリとの共同生活 を維持するには、とにかく先立つものが必要だった。 最初に勤めたのは、夜間警備のアルバイトだ。深夜の工事現場に赴き、誘導灯を片手に車 の流れを見ているだけの簡単なお仕事。 ラーメン屋、コンビニ、町工場。これまで数々のバイトをロケットで突き抜けてきた俺だ が、この仕事は二週間近く続けられた。退屈になったり眠たくなったりしたときは、脳内で 音楽を再生して乗り切った。アルバムを丸一枚再生すれば六十分。そんなふうに刻んでいけ ば、時間は意外と早く過ぎていくものだ。 しかし生活の乱れから体調を崩し、結果このバイトは辞めざるを得なくなった。 警備員の次は、まんが喫茶の店員をやった。いっときはそこをねぐらにしていたのだ。仕 事の要領はそれなりに心得ている。 案の定、まんが喫茶での仕事は楽勝だった。ヒカリとの共同生活で身につけた家事のスキ ルも役に立った。調理、掃除は慣れたものだ。同僚がチャラいDQNばかりなのが苦ではあ ったが、彼らから学ぶものも多かった。中でも底抜けのポジティブシンキングと巧みな話術 は、就職活動を進めるうえでおおいに参考になった。 しかし店長の不祥事が発覚して店舗が休業となり、あえなくここでのバイトも引退に追い 込まれた。 辞めたり、クビになったり、ときには店そのものがなくなったり。 転々とアルバイトを変えながら、ちょっとずつ経験値を積んでいく。 そうやって半年が過ぎたころ、俺はとある企業の最終面接にまで漕ぎ着けた。 離職者があとを絶たず、慢性的な人員不足に陥っているブラック企業だ。 幸か不幸か、そこは俺もよく知っている会社だった。 「どうして彼がここに?」 「それが、一次二次三次と面接官にすこぶる評判でして……」 「SPIでも優秀な成績を残しているそうです」 「むかしとは一味違う、ってわけか」 八月、都内某ビル。 最終面接を受けにきた俺を見るなり、会議室に集まった役員たちはどよめいた。 コの字型に配置された長机、その真ん中で榊さんが渋い顔をしている。 尻尾を巻いて逃げ出したはずの男が、なにをしに戻ってきた? そんな顔だ。 一ヶ月まえ、榊さんの会社が中途採用で営業職を募集していると知り、俺は迷わずエント リーシートを送った。無論、過去にアルバイトとして入社し、三週間足らずで辞めた経歴は 伏せて。 別に古巣が恋しくなったわけではない。どちらかというと、嫌な思い出だらけだ。 だが、この不況下で職歴を持たない俺が就ける仕事は限られているし、この会社は新興の IT関連企業の中では業績が安定している。 なにより、榊さんを見返してやりたかった。 使い捨ての歩も活かせば金に成るってことを、この会社の連中に思い知らせてやる。 最終面接は、ほとんど俺と榊さんの一対一の対話だった。 「言っとくけど、うちの営業はSEより過酷だぞ」 「覚悟しています」 「サビ残だって毎日やってもらう。体力がないとできる仕事じゃない」 「引っ越し屋で一ヶ月間バイトしてました」 「システム関連の知識も必要不可欠だ」 「明日からリナカフェに毎日通って猛勉強します」 一歩も譲らない俺に、榊さんはゴルフ焼けした眉間にしわを寄せてう〜むとうなった。俺 の変わりように戸惑っているのが、ありありと見て取れる。 「いいだろう。最後に社長としてではなく、親戚として忠告しておこう」 榊さんは席を立ち、圧迫感のあるまなざしを俺に向けた。 「IT関連は廃人製造工場みたいなもんだ。地獄を見るかもしれんぞ」 わかりきったことをあまりにも大真面目な顔で言うので、不覚にも笑ってしまった。 脅しのつもりだったのだろうが、そんなもの俺には通用しない。 「地獄なら、もう散々見てきたよ」 ――働けない地獄に比べれば、働ける地獄なんて生ぬるい。 たじろいでほかの役員たちを見る榊さんに念を押す。 「雇ってくれますよね?」 「う、うむ……」 「ありがとうございます」 これにて面接終了だ。 退席する際、俺は役員一人一人とハイタッチしたい気持ちを抑えて深々と目礼した。 以後お世話になります、という意味を込めて。 三日後、ヒカリと暮らすマンションに、採用の通知が届いた。 IT事業本部システムインテグレーション推進事業部、というのが俺の新しい職場だ。 榊さんの会社の基幹事業はITソリューション。営業が顧客からシステム開発の仕事を受 注し、社内のシステムエンジニアがそれに応える。顧客の業種は製造に流通、金融に広告代 理店と色とりどり。要するに、パソコンあるところに顧客あり、というわけだ。 俺の仕事内容は主に新規顧客の開拓。少ない日で十、多い日は十五件の会社を訪問し、自 社製品の利便性をアピールする。必要とあらば接待も開く。基本的なビジネスマナーやシス テム開発に関する専門知識は、新人研修で徹底的に叩きこまれた。 絞りカスも出ないくらいへとへとになり、マンションに戻るころにはソファに倒れこむ体 力しか残っていない。そんな生活が二ヶ月ほど続いた。 営業の仕事は想像以上に激務だった。移動に体力を奪われ、上司の嫌がらせに精神力を奪 われる。慣れないうちは毎日のように会社のトイレでゲロを吐いた。辞めたいと思ったのも 一度や二度ではない。 それでも俺は、ゲロを吐きながら死ぬ気で働いた。 へこたれそうになったときは、親父の言葉を思い出した。 ――働く才能なんかなくたって、情熱さえあれば、俺は戦える。 自分に鞭を打ち、まさしく馬車馬のように働き続けた。 そうしているうちに、いつの間にか季節は秋になり、俺は二十五歳に、ヒカリは十八歳に なった。 そんなある日、彼女の心境にちょっとした変化が訪れた。 一日の成果を報告書にまとめ、マンションに帰ると午前一時になっていた。 「おかえりなさい。お風呂にする? ご飯にする? それとも……」 「悪い、眠気がもう限界だ」 「だと思った」 くすりと笑い、俺が脱いだネクタイと上着を受け取るヒカリ。 最近、彼女はちょっとずつ笑顔を取り戻しつつある。 顔を洗ってソファに横になったところで、テーブルに真新しいフリーペーパーが積んであ るのに気がついた。カラオケや飲食店で配布されている求人情報誌だ。 「どうしたんだ、これ」 手に取ってみると、ところどころに付箋が貼られたり、マーカーが引かれたりしていた。 ヒカリは俺のとなりに座り、もじもじとうつむきながら答えた。 「私も働こうかなって」 「なんでまた急に?」 「急じゃないよ。頑張ってるサトシを見ていたら、私も頑張りたくなったんだ」 「ヒカリ……」 感無量だった。俺は疲れてぐったりしていたのも忘れ、彼女を強く抱きしめた。 「ちょ、ちょっと。汗臭いよ」 「汗は働く男の勲章だからな」 「……ばか」 この夜、俺たちは明かりを消した部屋で派手に祝砲をあげた。 それも二発や三発じゃない。若さに任せて、どかんと五発。 一年半近いヒカリとの共同生活で、もっとも幸福な夜だった。 「私ね、お金を貯めてまた声優目指そうと思うの」 毛布の中、俺の腕を枕にしてヒカリは言った。 「絶対に声優になって、テレビにもいっぱい出て、お父さんを見返してやるんだ」 「できるさ、ヒカリなら」 俺にはそれが、本当に不可能ではないことのように思えた。 なぜならヒカリは、俺と苦楽をともにした、かけがえのない戦友だからだ。 ――地獄を生き抜く強さがあれば、どんな夢だって夢じゃないさ。 このあとヒカリの前途を祝してもう一発でかいのを撃ったのは、アグネスにも石原都知事 にも言えない、二人だけの秘密だ。 しかし、なにもかもが順風満帆というわけにはいかなかった。 榊さんの会社で働きだして半年が経った二月のある日、俺が外回りの仕事を終えてオフィ スに戻ると、職場の同僚たちが血相を変えて詰め寄ってきた。 「おいサトシ、おまえなにやらかしたんだよ!」 「話が急すぎるってんで、人事のやつらカンカンに怒ってるぞ!」 「……なんの話だ?」 首をひねる俺に、同僚の一人が教えてくれた。 「おまえがクビになったって話だよ!」 聞けば、榊さんから直々に解雇処分が下され、社内は穴埋めに大わらわらしい。 同期で入社した連中は、自分もいつクビを切られるかと戦々兢々としていた。 原因をいろいろと考えてみたが、思いあたる節がない。進行中の案件はどれも首尾よく運 んでいたし、自分で言うのもなんだが、顧客の評判も悪くないはずだった。最近は酒に強い ところが上司の目に留まり、社内でも接待要員として重宝されている。 とにかく説明をということで、俺は複数の同僚を伴って社長室に赴いた。 「納得できません! どうしてこいつがクビなんですか!」 「そうですよ! こいつが頑張ってるの、社長だって見てたでしょう!」 いまいち状況を把握しきれない俺よりも、同僚たちのほうがよっぽど熱くなっていた。 彼らの真剣そのものの横顔を眺めながら、俺はまったく場違いなことを考えていた。 ――いつの間にか、こんなにたくさんの仲間が俺を支えてくれている。 俺には、それが嬉しくて嬉しくてしかたがなかった。 榊さんはデスクワークをする手を止めて、悲痛な面持ちで言った。 「サトシくんのクビを切ったのは私じゃない」 「じゃあ、いったい誰が?」 「渡貫茂だ」 同僚たちの間に動揺が走る。 俺は黙って榊さんの話に耳を傾けた。 「TOBで三分の一以上の株式を集め、渡貫茂が我が社の経営権を取得した。サトシくんの 解雇は彼の指示だ」 「ちょ、ちょっと待ってください。それってつまり、買収されたってことですか?」 「すまない。私の力不足だ」 椅子から腰を上げ、申し訳なさそうに頭を下げる榊さん。 同僚たちはうろたえていたが、俺の頭は冷静さを保っていた。 ついに来たか、シゲル。 はるか高みから俺を見下してほくそ笑むやつの姿が、容易に想像できた。 「サトシくん、助けてやれなくて本当にすまない」 榊さんは俺の前に進み出て、頭を床につけて謝罪した。その声から彼の無念が伝わってく る。 「顔を上げてください、榊さん」 「サトシくん……」 「俺はあなたを恨んではいない。半人前のまま会社を去るのは惜しいが、それだけだ」 遅かれ早かれこうなることは覚悟していた。 家政夫を辞めて挑戦状を叩きつけたあの日から。 シゲルとの戦いは、すでにはじまっているのだ。 やつがどうやって俺の職場を探り当てたのかは知らないが、そうやすやすと勝たせてもら えないだろうことは百も承知している。 今までお世話になりました、と礼を言い、俺は社長室を出た。抱えている案件をほかの社 員に引き継がせたりデスクを整理したりと、やるべきことはたくさん残っている。 「ほ、本当によかったのか?」 デスクに戻り私物をダンボール箱に詰めていると、同僚の一人がそう訊ねてきた。 俺はできるかぎり鷹揚にうなずいて答えた。 「もとの生活に戻るだけだからな」 まったく未練がないと言えば嘘になる。ようやく仕事にも慣れ、職場の仲間たちにも愛着 を感じはじめていた。 だが、すべてが水泡に帰すわけではない。 この会社で働いて得た経験値は、しっかり俺の中に蓄積されている。 それは明日からの就職活動に必ずプラスになるはずだ。 どこまでも俺を追ってこい、シゲル。 俺がこの程度で諦めると思ったら大間違いだ。 働いて働いて、絶対にビッグな男になってやる。 ――俺のやる気とあんたの財力。どちらが長く続くか、根比べといこうじゃないか。 カスミがマンションを訪ねてきたのは、俺が榊さんの会社をクビになった翌日だった。 その夜、俺は就職支援サイトで求人情報を漁るかたわら、誤字脱字がありはしないかと履 歴書をチェックしていた。ヒカリは声優の養成学校に行っていて、部屋には俺一人だった。 チャイムが鳴って玄関のドアを開けると、思いつめた表情のカスミが立っていた。 彼女はその大きな胸に、革製のアタッシュケースを大事そうに抱えていた。 「どうしてここがわかったんだ?」 「シゲルさんがあなたの勤めている会社を調べ上げたときに、現住所がここだってわかった んです。今日は折り入ってあなたに頼みたいことがあってここに来ました」 「……どうやらただの家出じゃなさそうだな」 俺は彼女を部屋に招き入れ、テーブルにコーヒーを用意した。よほどあわてて家を飛び出 してきたのか、二月だというのにカスミはコートもマフラーも身につけていなかった。寒さ で手がかじかんでいる。 「頼みってなんだ? シゲルに関することか?」 カスミが勝手に外出することは、シゲルによって固く禁じられている。言いつけを破れ ば、肉体的にも精神的にもつらい罰が下されるはずだった。 そのリスクを冒してまで俺に会いにきたのだ。よほど特別な事情があるに違いない。 カスミはコーヒーに手をつけず、くぐもった声で言った。 「実は、あの人から手を引いてもらいたいんです」 「復讐を諦めろと?」 「はい。あの人はあなたを追い出すために、私財を投じて会社を買収しました。こんなこと を続けていれば、いつかあの人は破滅してしまいます」 「そうなれば願ったり叶ったりだな」 第一、シゲルは投資信託会社の社長である以前に凄腕の投資家だ。一部の経済紙の試算に よれば、やつが保有する個人資産は数百億にのぼるという。会社のひとつやふたつ買収した ところで、懐につく傷はかすり傷程度だろう。 いや、そういう問題ではない。 もはや俺にとって、シゲルへの復讐は人生そのものなのだ。 いかな事情があろうとも、それをこんなところで終わらせるわけにはいかない。 「お願いします! あの人には時間がないんです!」 「時間がない……?」 「これを見てください」 カスミはアタッシュケースをテーブルに乗せ、ロックを外して俺の手もとに滑らせた。 中から出てきたのは、カルテとおぼしき書類の束と、二枚のX線写真。 写真は脳の断面を撮影したもののように見受けられた。 青い脳の中央に、毒々しい果物の種のような赤色が浮かび上がっている。 「これって――」 「病気だったんです、あの人」 どくん、と心臓が震えあがった。 ヒカリが手首を切って搬送された病院で、シゲルは商談のためにここに来たのだと言っ た。俺はそれを真に受けて、やつのオフィスに病院関係の書類を届けたときも、医療器具販 売のビジネスでもはじめるのだろうと思っていた。 だが違っていた。 シゲルはずっとまえから病気を患っていたのだ。 「パーキンソン病と呼ばれる難病です。現在の医学では、完璧な治療は困難だと言われてい ます」 カスミの悲痛な声が、幻聴のようにぼんやりと遠くなる。 シゲルへの復讐は、俺の人生そのもの。 ――やつがいなくなってしまったら、俺はどうすればいい? 人生が、消えてゆく。 急に頭がふらつき、俺は椅子の上でバランスを崩した。 カスミは震える声で、もう一度言った。 「あの人には、時間がないんです」 俺とシゲルの復讐対決は、大きな転換点を迎えようとしていた。 |
| ≪prev round next round≫ |